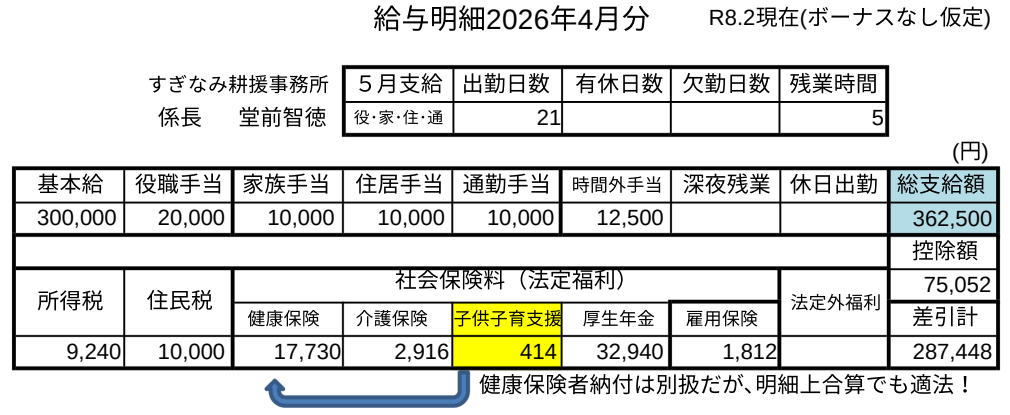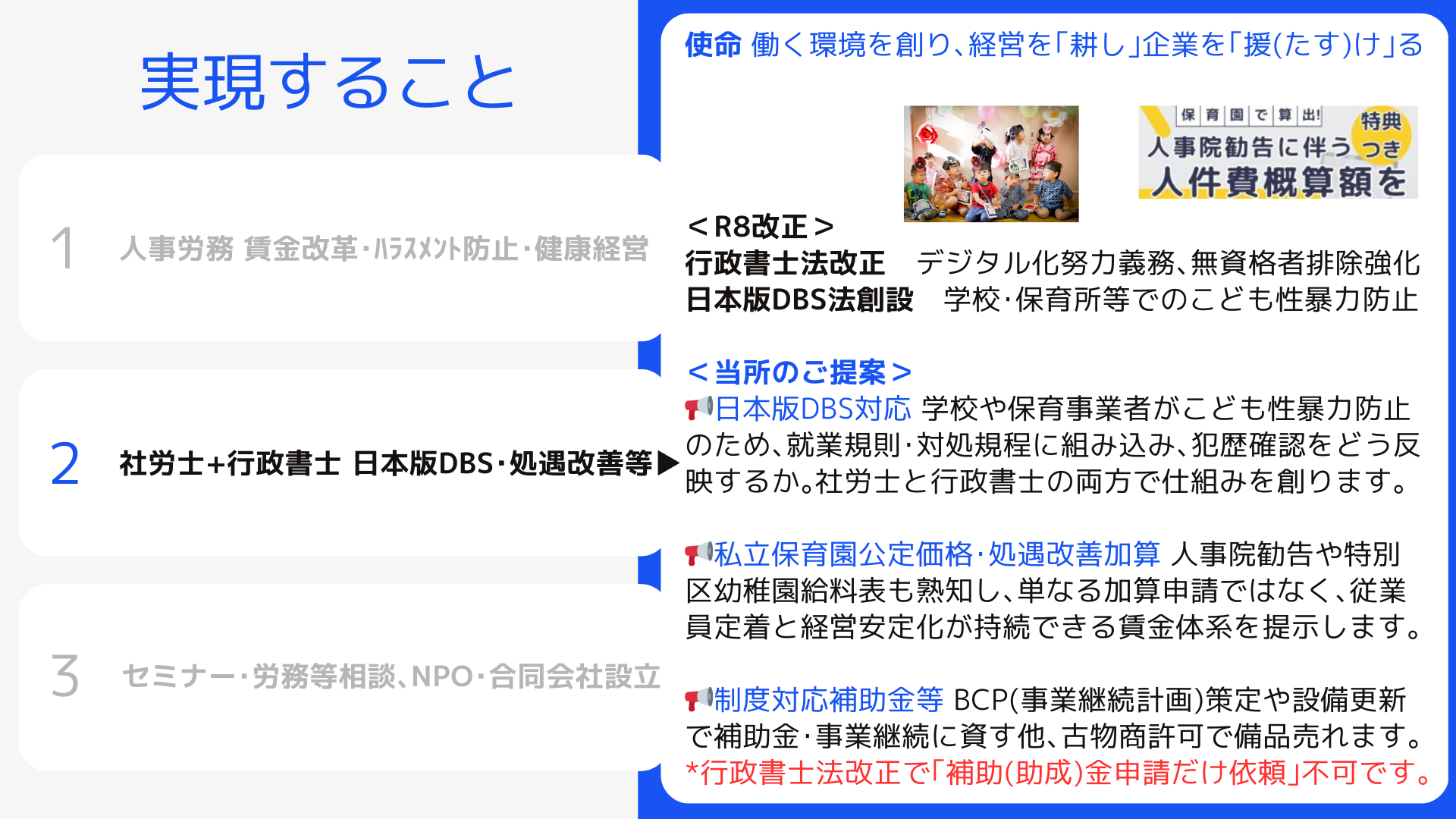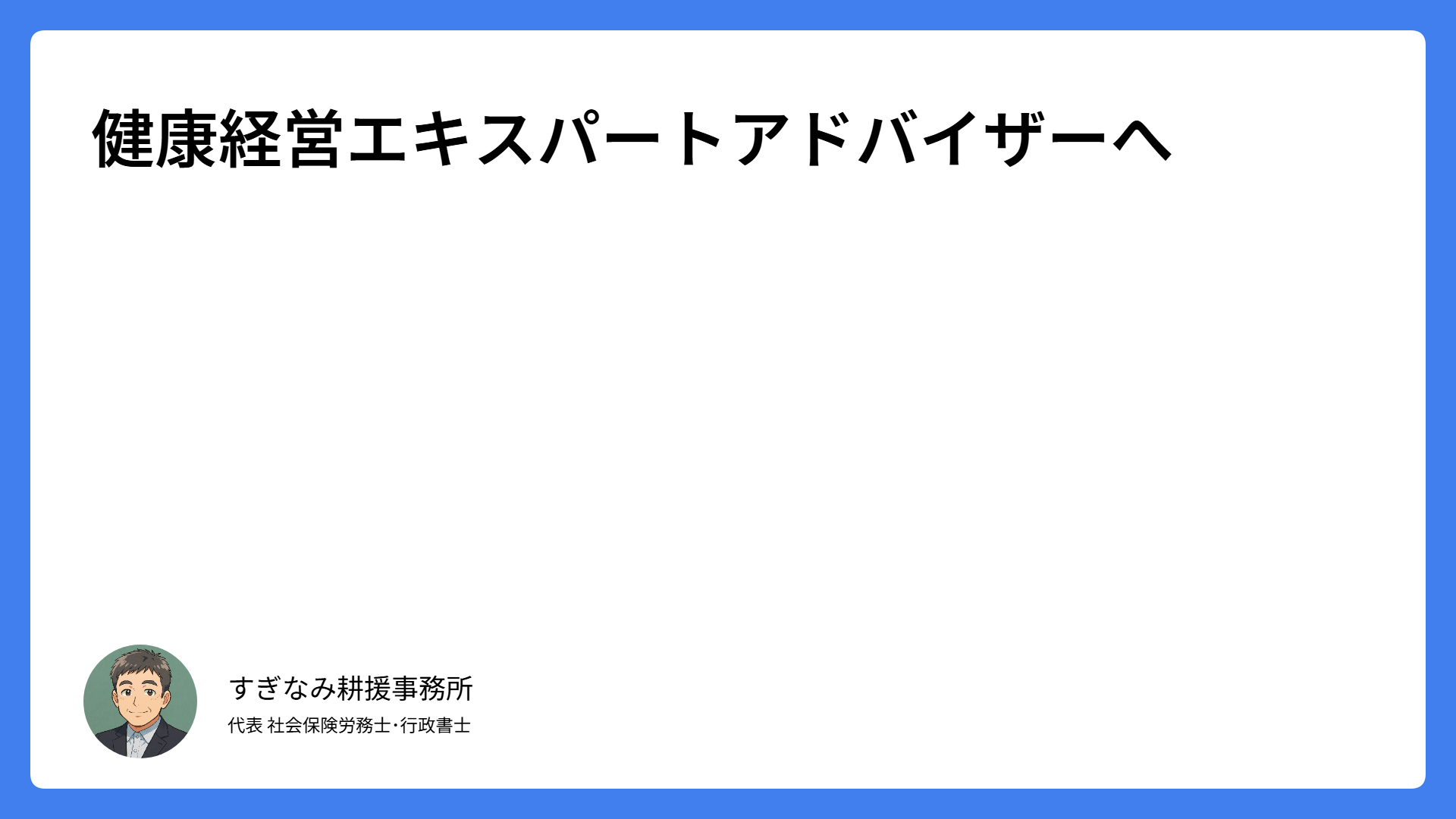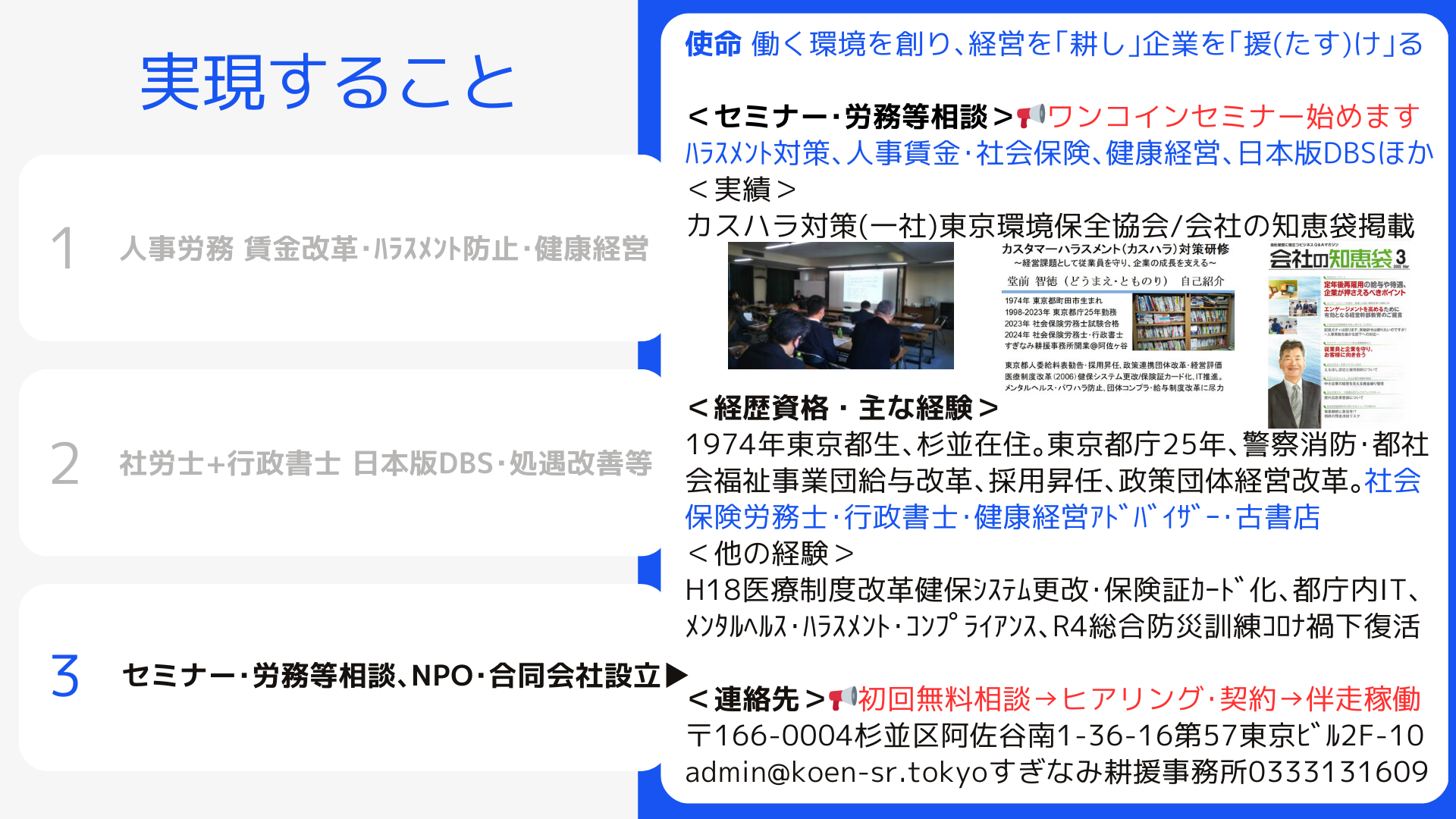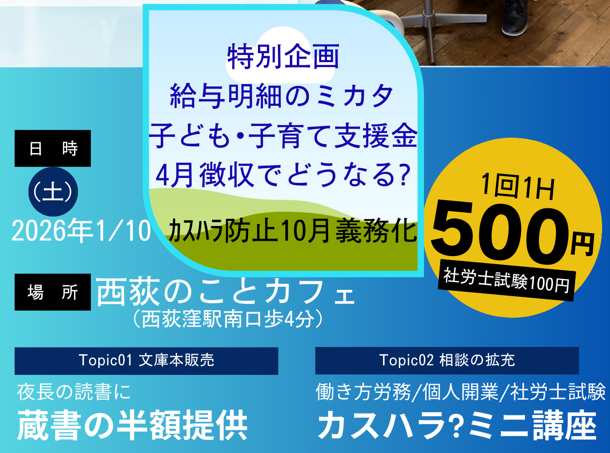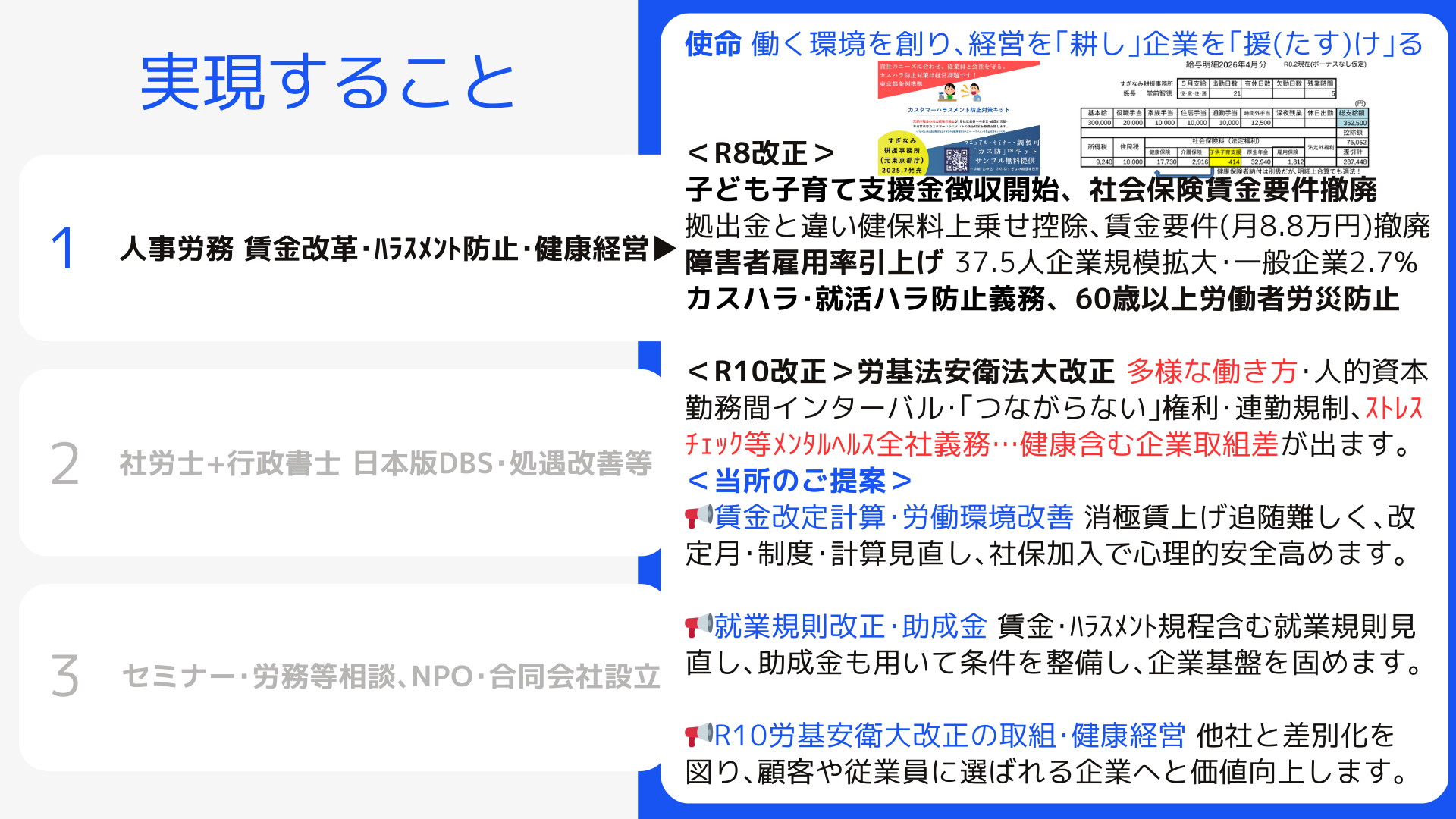R7社労士試験判例出題

判例対策が必須になっています。問題ページ数の多いその実は、判旨が長いことでページ数を稼いでいるからですし、全文を読む必要さえなく、備えていれば難しくないのです。
今年の出題
6つ判例が出題にありましたが、判旨を読み進め、例えば所持品検査は合理性有の西鉄だったな、と浮かぶ程の勉強が必要です。
- 小川「判例100」日本法令(第2版)
- 大内「判例200」弘文堂(第8版)
その2冊で十分、判例100選(有斐閣)は学者が多く携わり一貫性を欠きお勧めしません。滋賀県社協事件は最新判例ながら、片山組事件(平成10年4月9日最高裁)から類推できます。
択一式
選択式
- 東朋学園事件(平成15年12月4日最高裁判決)労働基準法
- 中央労基署長(労災就学援護費)事件(平成15年9月4日最高裁判決)労災保険法
- オリエンタルモーター事件(平成7年9月8日最高裁判決)労働一般常識
西日本鉄道事件
「使用者がその企業の従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なう、いわゆる所持品検査は、被検査者の基本的人権に関する問題であって、その性質上つねに人権侵害のおそれを伴うものであるから、たとえ、それが企業の経営・維持にとって必要かつ効果的な措置であり、他の同種の企業において多く行なわれるところであるとしても、
また、それが労働基準法所定の手続を経て作成・変更された就業規則の条項に基づいて行なわれ、これについて従業員組合または当該職場従業員の過半数の同意があるとしても、そのことの故をもって、当然に適法視されうるものではない。
(中略)問題は、その検査の方法ないし程度であって、所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならない。
そして、このようなものとしての所持品検査が、就業規則その他、明示の根拠に基づいて行なわれるときは、他にそれに代わるべき措置をとりうる余地が絶無でないとしても、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等、特段の事情がないかぎり、検査を受忍すべき義務がある。」
気を付けるべきは、本件「解雇無効の確認に係る訴訟」ですが、そのことが記されていても判旨ではない点です。また、時代背景も読みましょう、まだ労組も強い時期の私鉄です。択一式戻る
滋賀県社協事件
「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。
上記事実関係等によれば、上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容を本件業務に係る技術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから、被上告人は、上告人に対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかったものというほかない。」
かなり大きく報道されたのは、「職種限定」契約であり同意外の配転は不可との判旨からです。逆に片山組事件、いわゆるゼネラリストは工事現場監督できずとも、他の仕事は可能と申し出ているのに配慮しない会社が敗訴した判決です。択一式戻る
古河電工事件
「労働者が使用者(出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆる在籍出向)が命じられた場合において、
その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずるについては、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得る必要はないものと解すべきである。
けだし、右の場合における復帰命令は、指揮監督の主体を出向先から出向元へ変更するものではあるが、労働者が出向元の指揮監督の下に労務を提供するということは、もともと出向元との当初の雇用契約において合意されていた事柄であって、
在籍出向においては、出向元へ復帰させないことを予定して出向が命じられ、労働者がこれに同意した結果、将来労働者が再び出向元の指揮監督の下に労務を提供することはない旨の合意が成立したものとみられるなどの特段の事由がない限り、
労働者が出向元の指揮監督の下に労務を提供するという当初の雇用契約における合意自体には何らの変容を及ぼさず、右合意の存在を前提とした上で、一時的に出向先の指揮監督の下に労務を提供する関係となっていたにすぎないものというべきであるからである。」
まず「ベン図」を書きましょう。解雇や賃金支払の是非ではありません。出向元に人事権があると解れば、択一の選択肢の一つのため、それ以上読まずに先へ進めなければいけません。択一式戻る
東朋学園事件
「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。
そして、同法39条7項は、年次有給休暇請求権の発生要件である8割出勤の算定に当たっては産前産後休業期間は出勤したものとみなす旨を、同法12条3項2号は、平均賃金の算定に当たっては、算定期間から産前産後休業期間の日数を、賃金の総額からその期間中の賃金をそれぞれ控除する旨を規定しているが、これらの規定は、産前産後休業期間は本来欠勤ではあるものの、
年次有給休暇の付与に際しては出勤したものとみなすことによりこれを有利に取り扱うこととし、また、産前産後休業期間及びその期間中の賃金を控除しない場合には平均賃金が不当に低くなることがあり得ることを考慮して定められたものであって、産前産後休業期間を一般に出勤として取り扱うべきことまでも使用者に義務付けるものではない。
また、育児休業法10条は、事業主は1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものに関して、労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない旨を規定しているが、上記措置が講じられた場合に、短縮された勤務時間を有給とし、出勤として取り扱うべきことまでも義務付けているわけではない。
したがって、産前産後休業を取得し,又は勤務時間の短縮措置を受けた労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。
ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは、一応の経済的合理性を有するものである。
上告人の給与規程は、賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文書は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。
本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利及び育児休業法10条を受けて育児休職規程で定められた勤務時間の短縮措置を請求し得る法的利益に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、
上述のような労働基準法65条及び育児休業法10条の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、公序に反するものとして無効となると解する。」
かなり長い文言を選ばねばならず、ヒントもあまりなく、上記の判旨を読むと、「経済的合理性」など混乱させる記述もあります。言い回しも含め、「産休は権利で取得の制限はダメだな」「年休比較で産休無給はともかく取らせないのは…」と推定するくらい。ただし頻出判例です。選択式戻る
中央労基署長(労災就学援護費)事件
「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、労働災害補償保険法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、同法第3章の規定に基づいて行う保険給付を補完するために、労働福祉事業として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。
そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、労働基準監督署長に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。
そうすると、労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、同法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」
テキスト上は、だんだん扱いが小さくなった印象です。当方は分かりますが「公権力の行使」も馴染まないです。ただ、頻出判例、保険給付は労基署長と理解なら回答可能でしょう。選択式戻る
オリエンタルモーター事件
「組合結成通知を受けてからE守衛事件まで約9箇月にわたり、上告人は、許可願の提出があれば業務に支障のない限り食堂の使用を許可していたというのであるが、そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂の使用につき包括的に許諾をしていたものということはできず、その取扱いを変更することが許されなくなるものではない。
一方、E守衛事件が起きた直後に上告人から会場使用許可願を却下されて以来、組合は、上告人所定の会場使用許可願用紙を勝手に書き変えた使用届を提出するだけで、上告人の許可なく食堂を使用するようになり、こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで5箇月近く続けていたのであって、これが上告人の施設管理権を無視するものであり、正当な組合活動に当たらないことはいうまでもない。
上告人は、組合に対し、所定の会場使用許可願を提出すること、上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得ること、排他的使用をしないことを条件に、支障のない限り、組合大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって、
このような提案は、施設管理者の立場からは合理的理由のあるものであり、許可する集会の範囲が限定的であるとしても、組合の拒否を見越して形式的な提案をしたにすぎないということはできない。
また、上告人は組合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用させることとし、外部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も、上告人の施設管理権を過少に評価し、あたかも組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であって、
組合による無許可使用の繰り返しの事実を併せ考えるならば、上告人の施設管理権を無視した要求であると上告人が受け止めたことは無理からぬところである。そうすると、上告人が、E守衛事件を契機として、従前の取扱いを変更し、
その後、食堂使用について施設管理権を前提とした合理的な準則を定立しようとして、上告人の施設管理権を無視する組合に対し使用を拒否し、使用条件について合意が成立しない結果、自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用させない状態が続いたことも、やむを得ないものというべきである。
以上によれば、本件で問題となっている施設が食堂であって、組合がそれを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえないこと、組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認められないと企業内での組合活動が困難となること、上告人が労働委員会の勧告を拒否したことなどの事情を考慮してもなお、
条件が折り合わないまま、上告人が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、上告人の権利の濫用であると認めるべき特段の事情があるとはいえず、組合の弱体化を図ろうとしたものであるとも断じ得ないから、上告人の食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるということはできない。」
労働組合法は出題しにくいことも手伝い、今後も判例の形で出題が高まるでしょう。「施設管理(権)」を思い出すかは、実はC「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」のパワハラ出題にあり、労働施策総合推進法の改正=カスハラは出題対象外も、施設管理権を根拠に出禁は重要対策で実務者は連想できます。「組合の弱体化~」は他の判例にも見られる表現です。選択式戻る
何のための出題か。後知恵でも、労務管理上起こる実例と捉え、暗記対象とはなりません。